ブレインパッドは年間300回以上の勉強会が自主的に開催されており、学習意欲の高い人材が集まっています。そんなブレインパッドには、入社前に学業や研究活動に力を入れていた社員も多く在籍しており「指導教員×社員シリーズ」として、大学や大学院などでの学びが、今の業務にどう活きているのかを探っていきます。今回はシリーズ第2回として、筑波大学の粉川先生と、その指導を受けた当社データサイエンティスト飯田さんにお話を伺いました。

お話しいただく二人のプロフィール
粉川 美踏 先生
筑波大学 生命環境系 准教授
2014年、東京大学 大学院農学生命科学研究科博士課程修了後、農業・食品産業技術総合研究機構でポスドクとして在籍。2015年10月に筑波大学に助教として着任、2024年より現職。食品工学における食品の加工や非破壊評価を専門としている。
飯田 大希
株式会社ブレインパッド アナリティクスコンサルティングユニット所属 データサイエンティスト
2023年、筑波大学大学院 理工情報生命学術院 生命地球科学研究群 生物資源科学学位プログラム修了後、ブレインパッドに入社。3か月間の新入社員研修終了後、情報サービスや医療、小売などの幅広い業界のプロジェクトを経験し、現在は製造業におけるプロジェクトで業務に取り組む。データサイエンティストとして既存システムの精度改善や、新規システムの機能開発、業務フローの整理など、さまざまな業務に携わる。
粉川先生と飯田さんの出会い・研究テーマ
木原
本日はよろしくお願いします。まず、お二人の接点について教えてください。
飯田
初めて粉川先生を知ったのは、大学1年次に受講した、粉川先生担当の物理学の講義でした。その後大学3年で粉川先生の「食品プロセス工学」の授業を受け、食品、工学どちらも興味がある中で自分にピッタリな領域だと思い、粉川先生の研究室を選びました。
粉川先生
当時、飯田さんの代で私の研究室に入ってきたのは飯田さん一人だけでした。同期がおらず、1つ上の先輩がたくさんいる中で「どういう研究テーマをやりたいですか?」と聞いた際に「あの研究は同じ技術をいろんなものに使い回している研究だから気乗りしない」「この研究は技術自体が新しいので挑戦してみたい」と回答が返ってきて、先輩がやっていることをしっかりと見ていて、鋭いなと感じていました。
木原
飯田さんは当時のことを覚えていますか?
飯田
研究室配属は4年次からですが、3年生の頃から実際に先輩の研究発表を聴講でき、先輩方の発表を踏まえて「新しいテーマにチャレンジしたい」と思っていました。ちょうど1つのテーマが基礎段階という状況だったので、それを応用化するような研究に取り組みたいと思い、研究テーマを選びました。大学・大学院では、レーザー散乱法と呼ばれる非破壊技術を用いて、農産物の力学的特性(食感に関連する特性)を予測することができないかという研究テーマに取り組んでいました。実際の研究ではりんごを対象として、取り組んでいました。

木原
粉川先生の指導内容で印象的なところはありますか。
飯田
研究内容を知らない人に対して、どうやって伝わるように説明するかを学べたと思います。例えば、スライド作成やポスター発表の際にも「研究の目的や流れをより伝えるために、こんな風に表現を変えたほうがよいのでは?」などのアドバイスをいただき、人に伝えることの重要性を理解できました。
粉川先生
私自身が在籍していた食品総合研究所時代の上司が、企業からアカデミアに来た方だったということが大きいかもしれません。その方の目線として「幅広い人に対してわかりやすく伝える」という点を常に意識していて、技術のネーミングにもこだわりがあったんです。「どんなに正確であっても、アカデミックで難しい名前だと誰も食いつかない」という点を気にかけていました。アウトプットが上手な方で「正しいけど、誰も興味を持ってくれないのでは」と指導を受けることがあったので、そのマインドは自分でも大事にしていたように思いますね。今では、伝え方のハウツー本も出ていますし、情報化社会の中でどうやって目立つかというノウハウもあると思うのですが、私の上司は10年、15年前から言及していたので、伝え方の部分は、特に強く意識していたと思います。
木原
飯田さんは、粉川先生の指導で、今でも自分の仕事に活きているなと思うことはありますか。
飯田
タスクに取り組む際に、まずはタスクの全体感を掴むという癖がついたところです。というのも研究室の方針に「1人1テーマに取り組む」というものがあり、私も1つの研究テーマを担当していました。その際に、研究背景、目的、方法を自主的に考える必要がありました。もちろん粉川先生のサポートもありつつ取り組んでいきましたが、この過程で全体感を掴む癖がついたと考えています。現在のデータサイエンティストとしての業務でも、顧客の課題や要望を把握し、それらを解決したり、叶えたりするために、どういうアプローチを取るべきか、どう細かいタスクに分割するかといった点で学生時代の考え方が活きていると思います。
木原
一般的な研究室だと、 2人で1テーマに取り組むことも多いのでしょうか。
粉川先生
同時に複数人で1テーマに取り組むこともありますし、よくあるのは、1つのテーマを代々受け継いだタイプの研究をする研究室は多いような気がしています。私たちの研究室もある程度の引き継ぎはしていますが、それぞれの学生が背景の部分から目的・方法をきちんと考えないといけないような仕組みになっていると思います。「1人1テーマ」の方式だとゼロからある程度考えなきゃいけないので、時間はかかってしまうのですが、考える力はつくかもしれないですね。
木原
ちなみに飯田さんは、どのようにして研究のテーマを決めたんですか。
飯田
研究テーマというより、なぜレーザー散乱法という技術を選んだかになりますが、大きく2点あります。
そもそも個人的な気持ちとして、大学・大学院を通じて、「このテーマを1つ成し遂げた」と言えるようなことをやりたいと思っていました。その中で私が選んだ技術が「初期段階の研究」であったため「実際の食品へ応用したい」と思い、テーマを選びました。
もう1つは、自分がかつて苦手だった領域に再チャレンジしたいという気持ちの部分です。
レーザー散乱法は光学計測の一種ですが、私自身、高校や大学で光学に対して苦手意識を持っていました。とはいえ心残りもあったので、研究テーマにして苦手意識をなくしてしまおうと思い、食品工学の中でも粉川先生の研究室を選びました。
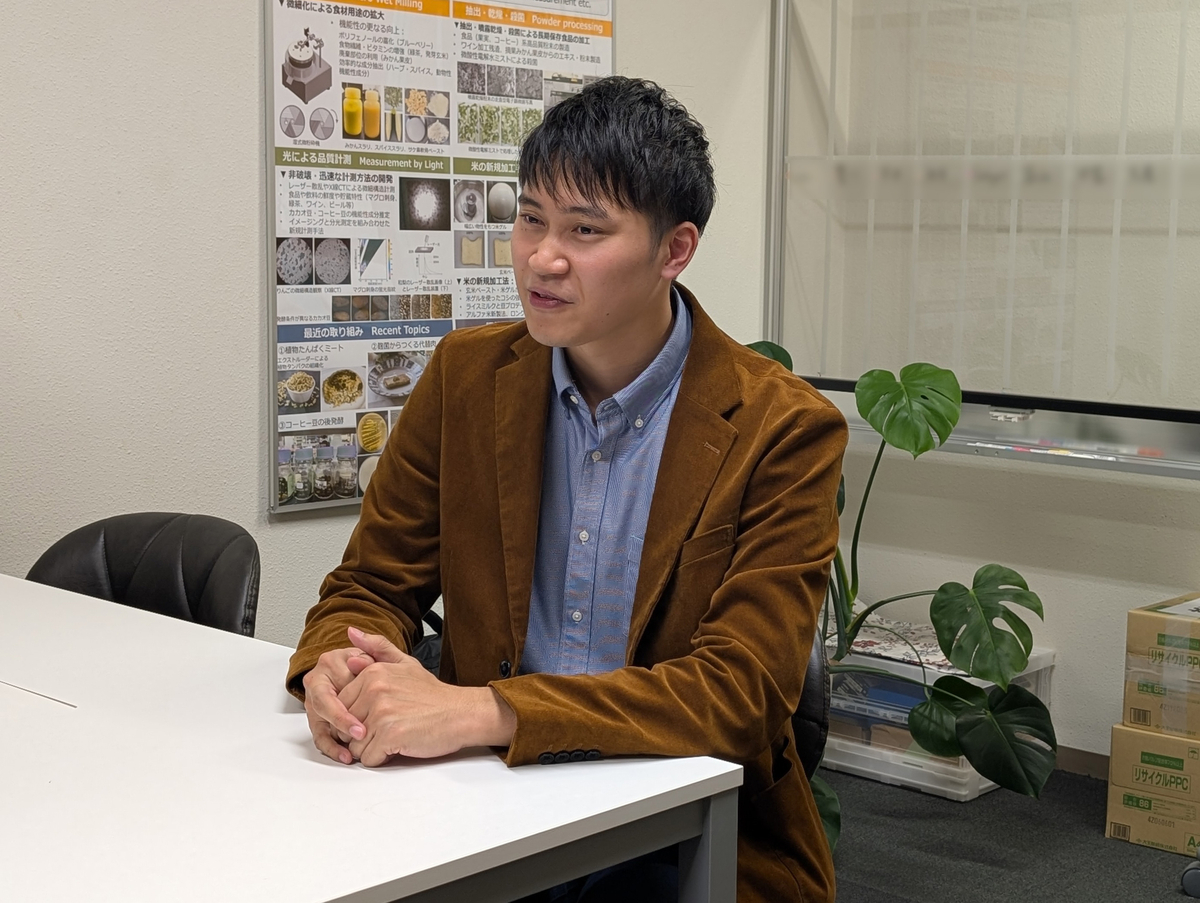
研究室での学びと現在のデータサイエンティストとしての業務
木原
粉川先生は飯田さんの研究への取り組み方や、研究している様子を見て、どんな社会人になると想像されていましたか?
粉川先生
飯田さんは、どこに行っても大丈夫だと思っていました。「1人1テーマ」という研究室の方針もあったのですが、人数も多くて、私自身が1人1人に対して、明確なゴール・到達点を示せているわけではなかったんですね。私自身の頭の中には、大体の道筋がぼんやりとありはするのですが、飯田さんは、いつもその想定を超えるような形で進めてくれている印象でしたし「任せておけば大丈夫かな」と思っていました。自分のことをきちんと進めていくという道筋ができていたので、どこでも活躍できる人になるのではと思っていましたね。
また、1つ、印象的だったことに、メールでのやりとりがあります。私自身、担当学生が多い中で、 1人1人とのメールのやり取りも結構な数になってしまうのですが、例えば次の打ち合わせをするための日程調整のやりとりでも、人によっては5回ぐらいメールを往復する場合もあるんです。そこを、本当に最短で決まるようにメールを書いてくれていると感じていて、細かいところの気遣いは、おそらく社会人になった時にもよい印象につながるのかなと思っていました。
飯田
その点は研究室配属時から意識しているところかもしれません。というのも粉川先生が忙しいことは重々承知していたので、粉川先生がすぐに判断できるように、なるべく動いていました。この受け手を意識して自分が立ち回る意識は、クライアントワークでも活きているなと思います。
木原
以前、飯田さんから「粉川先生の研究室と、ブレインパッドの環境が近い」「自ら研究を進めようという人じゃないと辛いかもしれない」と話を聞いたことがあるのですが、研究室の在籍当時から「自律して進める」ことを意識されていたのでしょうか。
飯田
意識していました。またやはり「1人1テーマ」がその姿勢をより後押ししたと思います。1テーマの担当だと、月次報告や学会までにどのようにスケジュール立てるかを自己管理する必要がありました。この考え方はブレインパッドでの仕事でもかなり役立っています。実際、お客様からざっくりとした状態で依頼されることも少なくないため、どう依頼を解釈し解決するか、解決のためにどういったスケジュール感で進めるかいうことは、研究室での「1人1テーマ」における動きと同じプロセスを踏んでいるなと思っています。要するに研究活動時と、現在のプロジェクトで行っていることが非常に似ているなと感じます。
木原
粉川先生としては、飯田さんがデータサイエンティストになると聞いた際にどんな風に感じましたか。研究室としては、食品系の会社に行く人も多いと伺いましたが、そのときに思ったことがあれば教えてください。
粉川先生
そんなに実験は好きじゃないことも、そこまで器用ではないことも知っていたので、食品の開発などの、ものづくりや自分で作って食べて…ということをやっているイメージはあまり湧きませんでした。データサイエンティストそのものは、彼の強みも活かせますし、すごくぴったりだなと思いました。
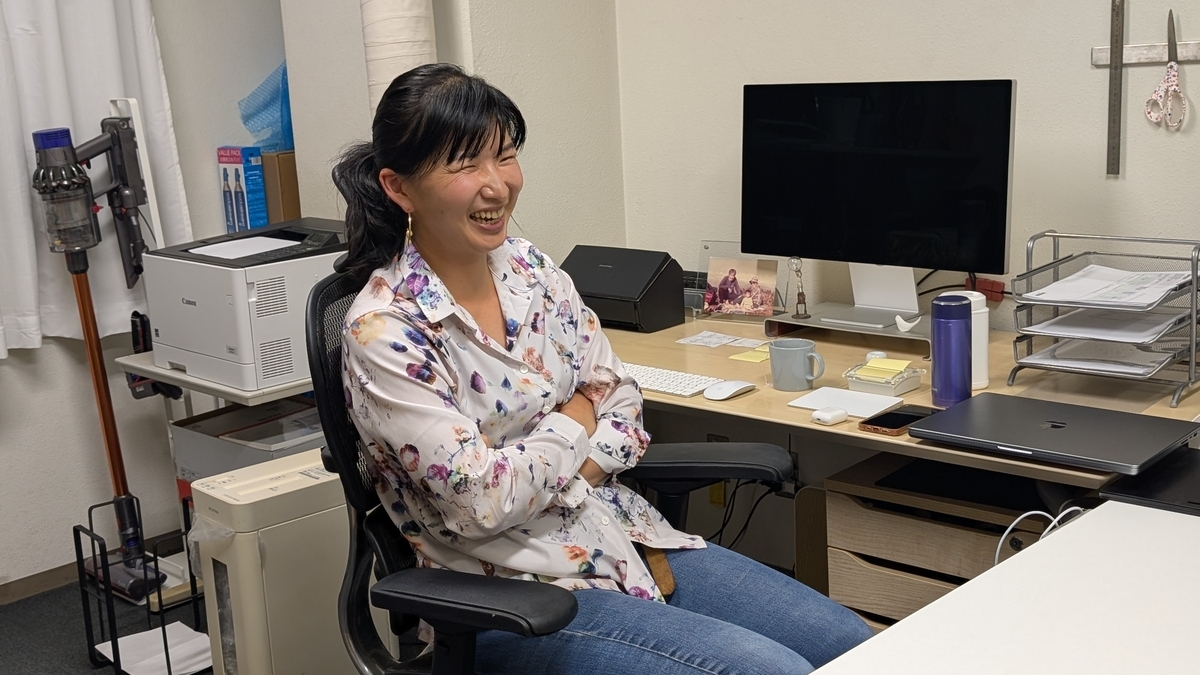
データサイエンティストとしての将来と、今後に向けて
木原
データ活用を仕事にしたり、社会にそれを活かしたりするために、どんな風にどんなことを学んでいくことが大事だと思いますか。
粉川先生
この先、おそらく実際のプログラミング能力の重要性がどんどん減っていくと思います。ただそれが全くないとできないこともあるので、基本的な解析とかプログラミングの技術があることは前提として、人間の抽象的な考えとか、抽象的な状況を、プログラミングという全てカチッと決まっている世界にいかに翻訳するかということが重要ですし、それに何回も取り組んでみることも大事だと思います。もちろん生成AIの出現でどう変わるのかはまだわからないのですが、お客さんが考えているふわっとしたことを、どうやって一つ一つのタスクに分けていくかみたいな能力がすごく必要なのかなと思いますね。
飯田
私もまさに同感で、そのふわっとした課題や要望に対して、どんな切り口で、現実的な問題に落とし込んでいくかということが重要かなと思っています。粉川先生もおっしゃったとおりLLM が台頭してきた時に、コードを書ける能力よりかは、ゴールから逆算したタスクの分割や、設定したタスクで本当に目的を達成できるのかどうかを判断する部分がより今後データサイエンティストに求められるのではないかと思っています。そのため、分析技術は前提におきつつ、顧客の要望を、どう細かな事象、タスクに落とし込んでいくかという部分が重要性を増していくのかなと思います。
木原
飯田さんとしては、今後データサイエンティストとして、こんな風に成長していきたいという将来像はありますか。
飯田
分析技術については、取れるアプローチの幅を広げるうえで継続的に学んでいきたいと思っていますが、先ほど例に挙げたお客様の課題の整理については、言語化を含め想定以上に難しさを感じているので、論理的な思考力や言語化力をつけていきたいと思っています。また将来的には、プロジェクトをリードしていけるような人材になりたいと考えています。
木原
ドメインとして、研究室のテーマでもあった食品に関わってみたい思いはあるのですか?
飯田
興味自体はもちろんあります。とはいえ現在は幅広い業界を見てみたいと思っています。上司へのアサイン希望も業界は絞らず、むしろ前回、前々回に担当した業界とは別の業界を希望はしています。
木原
今のお話を伺うと、違うところにチャレンジしてみたいというのは、冒頭の研究テーマを選ぶ際の動機と、共通する部分があるなと思いました。
飯田
確かにそうだと思います。実際、現在のプロジェクトは、これまでのプロジェクトとは全く異なる業界の顧客となっています。とはいえ、これまでの知識が全く役に立たないかというとそうでもなく、お客様の課題解決や要望を叶える部分は共通だなとは感じています。また、たまたまだとは思いますが、研究時代に扱ったことのあるデータを扱う機会がそこそこ多い印象もあります。例えば現在のプロジェクトではSEM(走査電子顕微鏡)のデータを解析しているのですが、研究時にSEMの撮影や解析も行っていたり、DOORSの記事でも述べましたが、歯科業界のデータ活用でもX線CTのデータ解析を行っており、こちらも学生時代に撮影・解析を行っていました。希少な例だとは思いますが、このように一見、自分にとって未知の業界でも、研究時代の知識が活きるというのも面白いと思っています。
木原
飯田さんから、当時大学生・大学院生だった自分に、今の自分からアドバイスするとしたらどんなことを投げかけますか?
飯田
テーマの背景から目的、方法を考え、最終的なゴールまで成し遂げたことが一つの成功体験として自分の中にあるので、ありきたりですが、目の前にある研究テーマにどっぷり浸かって、より試行錯誤したほうがよいということ、そのまま研究を頑張って、目の前のことを頑張ればよいということを伝えたいです。
木原
粉川先生から飯田さんに対して、今後に向けてのメッセージがあればお願いします。
粉川先生
飯田さんが今後なりたい像を聞いていると、基本的には今の延長線上でさらによくなると思いますが、それで最後まで行くことはなくって、おそらくどこかでまた全然違うスキルが必要になると思うんですね。具体的には、上の立場になるとマネジメントみたいなところとか。今からそれを考える必要はなくて、ちゃんと目の前のことに取り組めばよいと思うのですが、そういう新たな段階が現れた時には恐れずに取り組んでみたらいいのではと思います。だんだん同じことをやり続けて、スキルが上がってくると、新しいことに取り組むのはちょっと怖いと思うのですが、そこで新しい段階に行くと見えるものも変わってくると思うので、ぜひチャレンジできる人材であってほしいと思います。
飯田
おっしゃる通りだと思っていて、プロジェクトもプロジェクトマネジャーとメンバーと立場が分かれていますが、プロジェクトマネジャーになるとタスクやメンバー、顧客などのマネジメントが主な仕事になると認識しています。ゆくゆくはマネジメントも経験したいですし、やりたいと思う一つのゴールでもあるので、恐れず取り組んでいければと思います。そのためにまずはメンバーとして課題整理やタスクの遂行などを高水準で取り組めるように精進したいと思います。
木原
本日はありがとうございました。
ブレインパッドでは新卒採用・中途採用共にまだまだ仲間を募集しています。
ご興味のある方は、是非採用サイトをご覧ください!
www.brainpad.co.jp
www.brainpad.co.jp
