
谷川嘉浩
京都市立芸術大学美術学部デザイン科 講師
1990年生まれ。京都市在住の哲学者。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。現在、京都市立芸術大学美術学部デザイン科講師。著書に『人生のレールを外れるための衝動のみつけかた』(筑摩書房)、『スマホ時代の哲学――失われた孤独をめぐる冒険』(ディスカバートゥエンティワン)、『鶴見俊輔の言葉と倫理――想像力、大衆文化、プラグマティズム』(人文書院)、『信仰と想像力の哲学――ジョン・デューイとアメリカ哲学の系譜』(勁草書房)など。
イノベーションには「哲学」が必要
西田
本日は素晴らしい講義をしてくださり、ありがとうございました!
平易な言葉を使いながら、哲学への道を解きほぐしてくれる感覚で、とても分かりやすかったです。これって本当に哲学なんだろうかと錯覚するくらいで、まるで友達と話しているかのようでした。
谷川さん
ありがとうございます。哲学は、どうしてもなじみが薄く、捉えどころがないように感じられがちなので、そのように言っていただけると嬉しいです。
西田
なじみが薄いと言いつつも、最近、テレビや書籍でもよく見かけるように、ビジネス界をはじめ社会的にちょっとした哲学ブームになってますよね。
谷川さん
そうですね。ビジネス界でいえば、イノベーションが求められる中で、Howへの投資だけではなく、会社の無形資産への投資が必要だという考えが、少しずつ定着してきたように思います。そういった中で、無形資産である経営者や社員の「知性」や「感性」を育み、刺激するものとして、哲学が注目されてきたのではないかと思います。
西田
哲学に触れることが日常になり始めているんですかね。一方で、フランスなどの欧米では、バカロレア教育にみられるように、学生の頃から哲学に触れていて、自分たちの思考を展開する上で、哲学が役に立つというのが深く染み渡っていると感じます。また、立ち飲み屋で、”哲学のテーブル”のごとく、ものすごい討論が繰り広げられているのを見たこともあります。日本でも、昭和初期に、貧乏学生達が四畳半の下宿に集まってそういった議論をするというのがあったわけですが、今は少ないのではと思っています。
谷川さん
日本では、哲学的に議論するという文化は、あまりないかもしれませんね。背景にあると考えられるのが、日本人の持つ抽象と具体の対比・捉え方があるのではと思います。
丸山眞男という思想家が言っていることですが、私たち日本人は、気持ちや思い、感覚といった「実感」をベースに反応や行動を組織することが得意です。一方で、海外のトレンドを追うのも好きですよね。研究者たちもそうで、海外の理論や抽象概念を好んで輸入しています。ここで問題になるのは、そういう実感主義と、理論主義がうまく交わっていないことです。哲学の議論では、具体と抽象が色んなレベルで交錯するからこそ「噛み合う」のですが、理論と実感が平行線の状態では、議論が深まらないんです。つまり、具体と抽象を行き来するとか、自分の感覚を捨てずに抽象にしがみつくことが必要です。そういった文化が日本では十分定着していない辺りに、哲学する習慣が根づいていない理由の一つがあるかもしれません。
西田
なるほど。そういった可能性はありますよね。
谷川さん
さらにいうと、明治以来の日本では、エリートの側は抽象だけ、民衆は具体だけのように、階級と対応してしまい、どちらの側も、抽象と具体を結びつけるという習慣を根づかせられなかったところがあるのかもしれません。。日本では、そうして両者を交差させる文化を持たないまま、抽象的な理論とのタッチポイントである「大学教育」ががマス化した。日本の大学教育が最初に大衆化したと言われる1960年代から70年代にかけて、学生運動が起きますね。当時運動に熱心に参加した学生は、大学で触れる抽象的な議論を、経済大国化しつつある日本の現実と結び合わせようと悪戦苦闘していました。全体としては、やはり話がデカくて雑駁な言葉が横行しがちで、抽象と具体が適切な交流を持っていたとは言えなかったと思います。今見受けられる「哲学」の隆盛が、一時期の流行で終わるかどうかは、抽象と具体の両方を交差させる文化が育めるかどうかにかかっていると思います。
西田
谷川さんのいう、日本人が、抽象だけ・具体だけと割り切ってしまっていることは、日本の国際競争力にも影響を与えていると感じます。
2023年度の世界デジタル競争力ランキング※で、日本は32位でした。ずっと低迷している理由は何かというと、欧米では、イノベーションのためにIT投資をしている一方で、日本は、効率化やコスト削減のためにITを使っているからだと言われています。谷川さんが講義でお話しされた、ロバルト・ベルガンディ『突破するデザイン』※で取り上げられた「問題解決のイノベーション」と「価値、意味づけのイノベーション」の2種類のイノベーションにあてはめると、日本は、問題解決の具体の部分に特化してきたことが、国際競争力でも下位に落ち込んでいる理由なのだと思います。
※スイスの国際経営開発研究所(IMD)が毎年発表する「世界デジタル競争力ランキング」において、最新(2023年度)の日本の順位は第32位に下落している。(IMD, World Digital Competitiveness Ranking 2023.
https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness-ranking/
)
※突破するデザイン ロベルト・ベルガンティ
https://amzn.asia/d/hH10p41
谷川さん
そう思います。少し話を拡げますが、就活生を見ていると、これまでの学びとは無関係に「プログラミングや英語のスキルを身につけたら有利だ」「この資格がある方がいいかも」というような話をしてしまう人がいる。でも、取ってつけたように問題解決スキルを身につけなくても、これまで身につけた知識や技術を再解釈・横展開すれば、別の道が開けるかもしれない。それに、みんなが話題にしている「問題解決スキル」に飛びついても、同じように考えている人と同じ土俵で勝負することになる。取ってつけたように頑張って身につけられる程度のスキルや資格は、誰だって頑張れば身につけられる。それなのに、そこであなたは自分の勝負を始めるんですか?」と思ってしまいます。
西田
就活生からよく質問されますよね。成長意欲は素晴らしいですが、もったいない。
谷川さん
もちろんプログラミングができることや、英語が使えることなどは、大きな能力の違いになりますが、しかし、それだけではないだろうと思います。具体的にいえば、感受性やセンス、直観などと呼ばれているものは、資格のように一定の手順を踏めば育まれるものではなく、時間をかけて耕すほかないものです。意味や価値の領域に関わるものですね。そういう領域を重視すると、他人と同じ土俵で戦わなくて済む。じゃあ感性を尊重しながら仕事をしようと思っても、感性的な領域を言語化することは難しい。漠然としたフレーズとか、精神論になりがちなんですよね。
西田
ベルガンディのいう意味のイノベーションは、意味や価値を再定義したり、新たなコンテクストをつくったりすることですが、スキルを身につけ実践する方法は、なんとなくの言葉でしか表現できない気がします。
谷川さん
そうですね。意味のイノベーションを起こすときには、自分の内側から始まって、だんだんと仲間を増やしていくという流れだとベルガンディは言っています。つまり、n=1をまず自分にしなさいというんですよね。自分を説得できないような意味をつくっても仕方がないから、市場などの外側から始めるんじゃなくて、自分の内側から始めて、次に2、3人の仲間を説得して、議論して、考えを育て、徐々に社内で広げて、そして市場にいくというプロセスをたどるのが適切だといっています。これがベルガンディの提案する、感性を尊重した企画のアプローチです。このくらいまでは言えるんですけど、「n=1をどう立ち上げるの?」とか、「n=2, 3に増やす相手をどう選ぶの?」といったことは、それこそ各人の感性に任されています。意味のイノベーションが問題にしている「意味=コンテクスト」をどうやって思いつくのか、どういう手順で拡げていくのかということは、フォーマット化されたノウハウには還元しづらいのだと思います。
しかし、哲学というジャンルは、多様な仮説の宝庫であり、いろいろな仮説を持つことは、いろいろな見方ができるということです。だとすれば、哲学を学ぶことで、思いつきにつながるさまざまな着眼点、情報整理の仕方などを持つことができるかもしれません。哲学が蓄えてきたいろいろな仮説が、私たちの感性や知覚をより敏感にしてくれるということです。
哲学により予想を超える多様な学びを手に入れる
西田
お話を伺っていて、荒木博行氏のラーニングパレット※を思い出しました。白と黒の絵の具しかなかったらモノトーンの絵しか描けません。そこに、何者になりたいがために狙って色を集めるのではなく、自分なりの仮説や体験から色を集めていく、つまり、哲学を学ぶことでいろいろな色が集まり、新たなものをクリエイションできるのだと思います。
※「学びを継続的に行っていくためには、自分が何を学んだのかを整理し、そして今後自分が何を学んでいくのかを定めていく「地図」が必要になります。その地図を、本書では「ラーニングパレット」と表現しました。」独学の地図より
https://amzn.asia/d/9l54P21
谷川さん
そう思います。ラーニングパレットをプラグマティストがよく使う言葉で言い換えると、「思想の自由市場」を自分自身の中にも持つべきだということだと思います。つまり、いろいろな考えが、どの結果に結びつくかわからない。自分の持っているどのカラーがいつ必要とされるかは、あらかじめ予測しても当たるとは限らないわけです。だから、私たちにできるのは、やっぱりいろいろなカラーを手に入れることしかない。私が哲学の強みだと思うのは、お互いを嫌い合うくらい対立した考えの人がいること。つまり、哲学が多様なカラーパレットの採取先になりうるので、非常に面白いんじゃないかなと思いますね。
西田
ある意味、そんなところが哲学の強みでもあり、面白さでもあるということですかね。
谷川さん
はい、そうです。「〇〇が知りたい」と思って学ぶこと、つまり、予想どおりのことを学ぶのはもうすでにみなさん実践していることですよね。しかし哲学では、自分の選択肢や想像を超える人に会えるんです。予想を超えた色との出会いがあるのが、哲学の楽しみの一つなんだろうと思います。
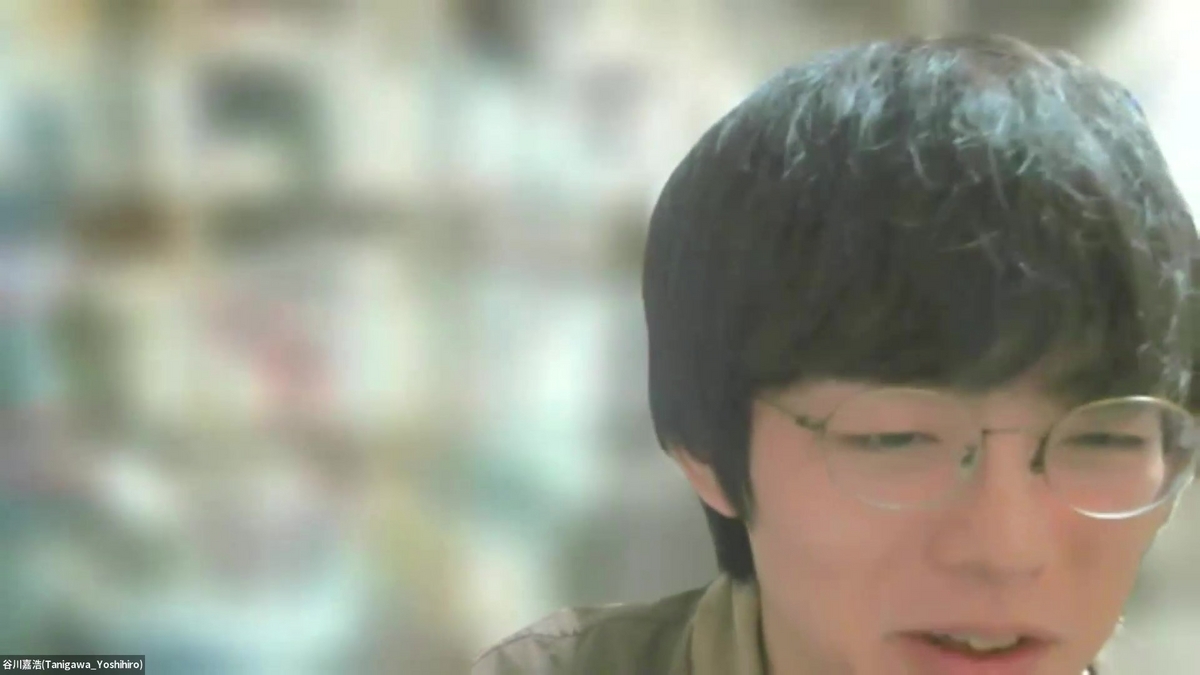

哲学を学び、イノベーションにたどり着くには「挫折」がおすすめ
西田
哲学を学ぶとき、何からどう始めるのがいいでしょうか?
谷川さん
カントの『純粋理性批判』の翻訳など、哲学書の翻訳に触れて、一度、挫折するのがいいと思いますよ。たぶん5ページくらい頑張ってめくったらもう嫌になるはずです。むしろ、それでいいんですよね。「自分には完璧に理解できるはずだ」という余計なプライドをへし折るために、まず早々にこけておくことが大事だからです。カントでなくても、誰か気になる哲学者がいれば、まず一回本人の言葉に触れて挫折し、しかるのちに入門書や解説書を開くという順序を覚えておいてほしいです。
西田
挫折すると、挫折しっぱなしの人が多いんじゃないかと思うんですけど、そういう人は諦めたほうがいいんですかね。
谷川さん
哲学者本人の言葉に触れるとき、「どうせ挫折する」というつもりで読むといいですよ。「これはこける練習だ」と言い聞かせながらこける感じです。組手の前に受け身をするみたいなもので、「まあ基本わからないな」を素直にスタート地点に置くと、その哲学者の思想を学ぶときの肩の力が抜けるんです。そうすると、少し学んだだけで、変にわかったかのような気になるみたいな、本当に避けるべき挫折を回避できると私は思います。過去の哲学者が言っていることは簡単ではないので、読めなくて当然だという姿勢で学ぶことをおすすめしています。
西田
意味のイノベーションにまで行き着くには、相当な道のりがありますね。
谷川さん
そうですね。そこが簡単じゃないから、意味のイノベーションを成し遂げるスキルは、コモディティ化しないんだと思います。あともう一つおすすめなのが、読んだことを人に説明することです。自分がどれだけ理解しているかがわかります。たとえば、カントがアンチノミーについてなぜ議論したのかを誰かに聞いてもらったり、ハンナ・アーレントの孤独と孤立の違いについて誰かに話してみたりするわけです。これが学びを深める大事なステップです。
西田
確かに、誰かの教師になることで、自分の理解の程度や不足が明らかになるんですね。それが、本当の学びにつながるわけです。
谷川さん
教師になることで、自分の興味がどこにあるかも見えてきます。たとえば、特定のトピックだけを繰り返し説明していることに気づくかもしれません。
西田
本を読んでいても、特定の章が特に面白いと感じることがありますから、それぞれの関心が多様性を生み出し、解釈を深めるんですね。
谷川さん
まさにその通りです。同じことを学んだはずでも、人によって異なる色をパレットに持ち帰ることになるのが、哲学の魅力の一つだと思います。
西田
最後に、このブログを読んでくださる皆さんに、哲学者として一言メッセージをお願いします。
谷川さん
「哲学者になろう」と振りかぶると、歴史が分厚いので実現は果てしない道のりになるでしょう。だから、もっと気楽に哲学とは付き合った方がいいと思います。少し古い比喩ですが、「置き薬」のように手の届く範囲に置いて、時々触れてみるのがちょうどいいのではないでしょうか。「本棚に哲学の本がいてもいいかな」とか、「家の近くにあるカルチャーセンターで哲学の講義やってるらしいね」とか、「哲学の研修ってありかも」とか、それくらいの親しさは感じてほしいなと思います。「哲学」と呼ばれる営みが世の中にあって、その輪に入りたいと思ったら入ってもいいんだと思えるように、みなさんの関心の縁に置いておいてもらえると、いつか助けになってくれるかもしれません。まずは家の中や関心の範囲にちょっと哲学を入れておいてもらえるというのがいいなと思います。
西田
それが谷川嘉浩著の本だったら嬉しいですね!
谷川さん
個人的にはそうですね! でも、なんでもいいと思います(笑)。
西田
改めて、今日は、ありがとうございました!
谷川さん
ありがとうございました!
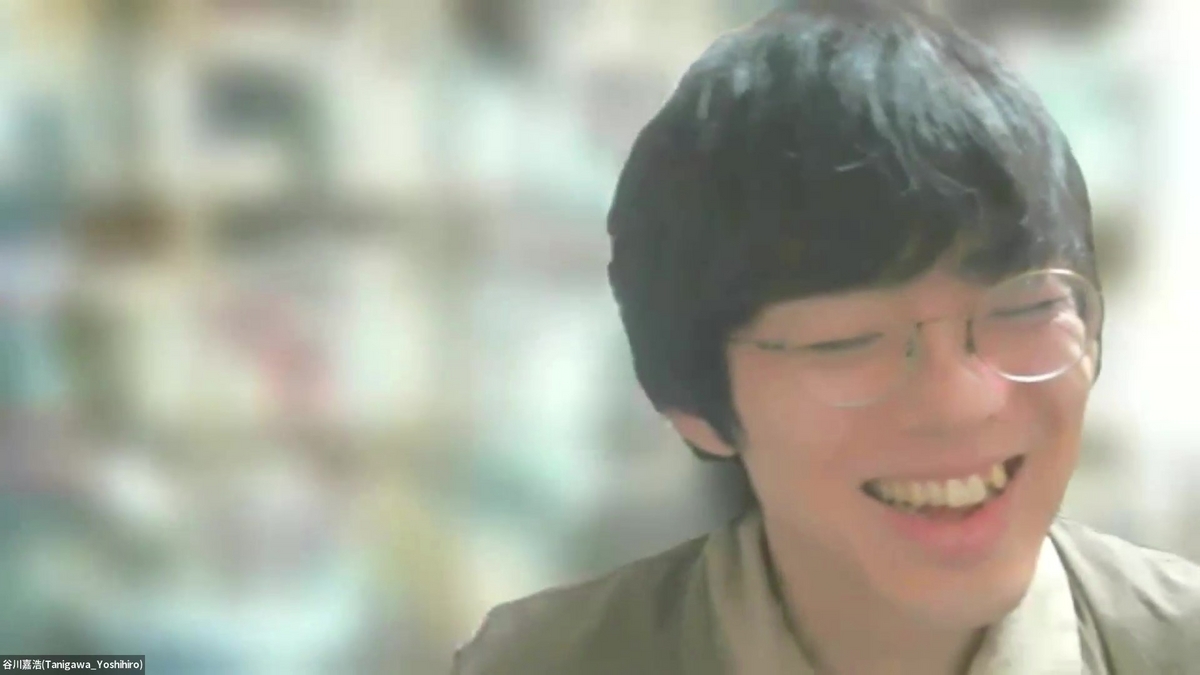

===================================================================
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
谷川さんの講義内容や、ブレインパッドにご興味をお持ちいただいた方は、ぜひ以下をご覧ください。
■谷川さん関連情報
note:https://note.com/houkago_kitsune/
X (Twitter):https://twitter.com/houkago_kitsune
著書『人生のレールを外れる衝動のみつけかた』ちくまプリマー新書
https://amzn.to/3wFmmQL
著書『スマホ時代の哲学 失われた孤独をめぐる冒険』Discover21
https://amzn.to/4byLh81
■ブレインパッドでは新卒採用・中途採用共にまだまだ仲間を募集しています。
ご興味のある方は、是非採用サイトをご覧ください!
www.brainpad.co.jp
www.brainpad.co.jp
